webライターはもういらない?AIとの差別化で将来性を高める方法を伝授

近年急速にAI技術が発展し、人間が書く文章と遜色のない記事が書けるまでに成長しています。
その影響から、巷では「もうwebライターはいらないのでは?」との声が増加。現役webライターの方や、これからwebライターを目指そうと考えている方はとても不安を覚えているでしょう。
しかし、webライターがもういらない職業だと言うのは嘘だと断言できます!その理由、およびAIと差別化して生き残る方法を現役webライターがご紹介しましょう。

Komita
・かくらぼ初代卒業生
・webライター独立後4ヶ月で月10万円達成(現在は月40万円前後)
・執筆記事は300以上
・金融領域の記事でGoogle1位を複数回獲得
・かくらぼライティング講師を2年6ヶ月経験
・現在は金融・人材領域のライティングとディレクター業を兼任
「AIあるからwebライターはいらない」が嘘である理由

早速ですが、AI技術があるからwebライターがいらない、との噂は嘘だと断言します。なぜなら、AIが肩代わりできる作業の質が不十分だからです。
たとえば最近耳にする「ChatGPT」。具体的な質問を入力すると文章を自動生成するスグレモノですが、出力される文章は「それっぽい内容をまとめたもの」に過ぎません。
さらに、専門分野の質問に関しては誤った情報を出力するケースも多々あるため、人間の手によるファクトチェックの手間が増えてしまうのです。
例として「令和5年度税制改正大綱」で定義された新しいNISA制度における「つみたて投資枠」の仕組みを説明する命令文を入力したところ、以下の誤情報が出力されました。
- 年間最大積立額80万円:つみたて投資枠では、毎年最大80万円までの非課税積立が可能です。これにより、個人の資産運用を促進し、将来の経済的な安定をサポートします。(正:年間最大積立額120万円)
- 最長10年間の運用期間:つみたて投資枠は最長10年間の運用期間を提供します。この期間内であれば、積み立てた資産を非課税で運用できます。(正:運用期間(非課税期間)は無期限)
実はChatGPTにインプットされている情報は2021年9月までのものしか無く、最新情報を取り扱うには別途Chromeの拡張機能「WebChatGPT」をインストールする必要があるのです。
このように、現状のAI技術が作成できる文章の質が低いため、webライターの仕事を完全に奪うレベルに達していないのが分かります。
AIの登場以外にも、webライターはやめとけと言われる理由については以下の記事で解説しています。
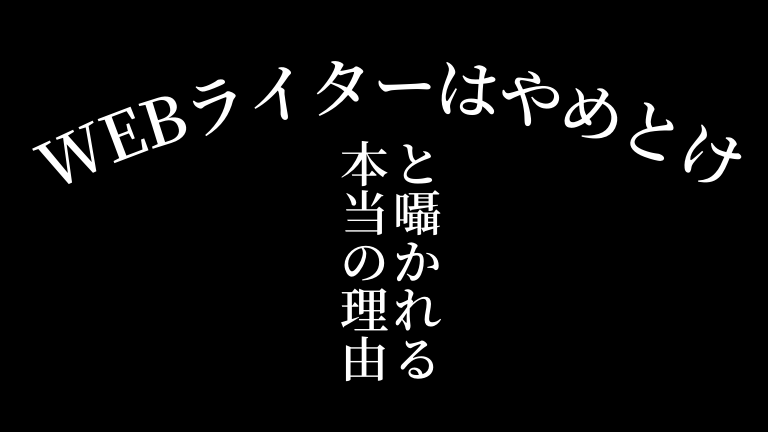
「AIに仕事を奪われるwebライター」は存在するので注意
「AIあるからwebライターはいらない」は嘘ですが、「AIに仕事を奪われるwebライター」は存在します。

どゆこと?って思いますよね
具体的には以下のような方です。
- AIが出力した文章をファクトチェックせずに提出する
- 他の記事をリライトするだけ
- ライティング以外のスキルがない(WordPress入稿ができない など)
まとめると「AIに任せっきり」「オリジナリティを意識していない」「文章を書くだけ」のwebライターは、近い将来AIに仕事を奪われる可能性が高いと言えるでしょう。
webライターいらない説を打破!AIとの文章を差別化する方法3選
ChatGPTやその他の高度なAIテキスト生成ツールが台頭していますが、真のライティングの価値は、単なる情報の提供や言葉の組み合わせではありません。
webライターがChatGPTなどのAIと差別化し、長く活躍していく方法を実体験も交えて解説します。
感性・経験(一次情報)・感情を盛り込む
AIが出力する文章は公的なデータなどを基に生成されるため、人の感性・経験・感情を含んだ内容は出力できません。
一方、webライターは執筆分野によっては「人間らしさ」や「実体験」が重要になることも多く、AIの文章に負けない大きな強みとなります。
また、AIが書く文章は「お硬い」印象が強く、柔軟性に欠けるのも玉にキズ。人柄や成功の秘訣が分かる文章の需要はまだまだ沢山あるのです。
直接の対話やインタビューをもとにした記事作成
AI技術は日々進歩していますが、直接人間と対話したりインタビューしたりできるものは存在しません。
対人コミュニケーションが得意な方であれば、対話で貴重な情報を引き出せるため、表面的なデータでは決して書けないディープな内容の記事が作成できます。
YMYL領域の知識を学び続ける
私個人の見解ですが、ChatGPTが出力するデータには誤情報も多いため、情報の入れ替わりが激しいYMYL領域のライティングには適していない印象を受けました。
「WhatChatGPTを導入すればいいのでは?」と思うかもしれませんが、最新情報を取得したAI文章をそのままコピペしていては、知識やライティングスキルが身につきません。
そのため、YMYL領域を扱うwebライターは、あくまでAIを作業効率ツールとして活用するのをオススメします。(作業効率化の方法は後述の「webライターがAIを有効活用する方法4選」で解説)
webライター自身にライティングスキルや専門知識が蓄積されていけば、AIが作成する構成や文章の修正およびファクトチェックが効率化され、質の良い記事が素早く書けるようになるのです。
他にも、webライターに将来性しかない理由について解説した記事を以下で紹介します。

webライターがAIを有効活用する方法4選
webライターがAIを活用して作業効率を上げるには、以下4つの方法を実務に取り入れるのがオススメです。(主にChatGPTの活用方法を取り上げます)
- タイトルの案を出してもらう
- 構成案を考えてもらう
- 文章の原案を書いてもらう
- WhatChatGPTに最新データをリサーチしてもらう
タイトルの案を出してもらう
たとえばChatGPTに「「AIがあればwebライターはいらないのか」という表題を解決する記事のタイトルを32文字以内で10個考えてください。」と質問をすると、以下のタイトルが返ってきます。
- AIとWebライター:協力の未来
- WebライターとAI:共存可能か
- AI vs. Webライター:課題と可能性
- WebライターとAIの新たな関係
- AIが変えるWebライターの役割
- Webライターの進化:AIの影響
- AIの台頭:Webライターの適応
- WebライターとAIの共存戦略
- AIとWebライター:共に発展
- Webライターの未来:AIの協力
そのまま使用するには不十分ですが、タイトルを考えるためのヒントとして利用できます。
さらに精度を上げたい時は、「「将来性」のキーワードも含めてください」など、潜在キーワードの使用を指示するのも効果的です。
構成案を考えてもらう
たとえば「「webライター いらない」というキーワードで執筆する記事の構成案を作ってください」と入力すると、以下のような構成案を出力してくれます。
イントロダクション
AI技術の進歩とWebライターの未来についての背景紹介。
AI vs. Webライター: 競合と共存
AIとWebライターの比較と競合関係について説明。
AIができることとWebライターが提供できる価値に焦点を当てる。
AIがもたらす利点と挑戦
AIが記事執筆に与える利点と課題について詳細に説明。
自動生成コンテンツの利用事例や成功事例を示す。
Webライターの役割再考
Webライターの新しい役割と適応戦略について考察。
創造性、戦略的思考、編集スキルなどの強化が重要であることを強調。
AIとWebライターの協力事例
AIとWebライターが協力し、相乗効果を生み出す例を紹介。
コラボレーションの成功パターンを提供。
Webライターの未来への展望
WebライターがAIと協力しながら成長する未来への洞察。
イノベーションと教育の重要性を強調。
結論
AIが進化する中で、Webライターがどのように価値を提供できるかの要約。
未来に向けた考察とアクションアイテムの提案。
この構成をwebライターがSEOに適したものに調整すれば、1から構成を作る手間がかなり省けます。

実はこの記事の構成もChatGPTに一部考えてもらいました!
文章の原案を書いてもらう
先程作ってもらった構成案の「AI vs. Webライター: 競合と共存」の内容を400文字で書いてください、と質問すると以下の文章が出力されました。
AI技術の発展に伴い、WebライターとAIとの関係は注目されています。まず、競合関係を考えましょう。AIは高速かつ効率的に大量のコンテンツを生成できます。これは一部の自動化されたコンテンツ生成プロセスにおいてWebライターと競合的です。
しかし、AIには限界があります。感情や創造性、特定のブランドのトーンとスタイルなど、人間のライターが提供する価値をAIはまだ完全に置き換えることができません。AIはデータに基づいて情報を生成しますが、独自の視点や深い理解を持ってコンテンツを創造することは難しいのです。
したがって、競合ではなく、共存が重要です。AIをツールとして活用し、Webライターの役割を補完することが可能です。AIはデータ分析やタスクの自動化に適しており、ライターはその情報をもとに洞察力に富んだコンテンツを生み出すことに専念できます。
最終的に、AIとWebライターは協力して、より効果的で価値のあるコンテンツを提供することができます。競合ではなく、共存の時代が到来し、WebライターがAIの進化に対応し、新しい機会を見つけることが鍵となります。
少々お堅い文章ですが、上記を手直ししたり間違いがないか確認していくと、1から文章を書く手間が省けます。
しかし、ファクトチェックに時間がかかる場合は、1から自分で書いたほうが早い時もあるので、やりやすい方を選んでください。
WhatChatGPTに最新データをリサーチしてもらう
たとえば「iDeCoの最新情報が分かる資料を出してください。」と入力すると、WhatChatGPTは以下の資料を解説付きで出してくれます。これはとても便利!
iDeCo(個人型確定拠出年金)の最新情報を入手するために、以下の情報源が役立ちます
iDeCo公式サイトは、iDeCoに関する情報や加入手続きについて詳細な情報を提供しています。こちらから最新のガイドラインやフォームを入手できます。
個人型確定拠出年金ナビ(iDeCoナビ)は、iDeCoに関する情報を包括的に提供しており、加入ガイドや金融機関のランキングなどの情報を提供しています。
モネックス証券のiDeCo情報では、iDeCoのメリットについて説明しています。セカンドライフに向けての資産づくりの詳細情報が提供されています。
三井住友信託銀行のiDeCo情報は、個人向け年金に関する情報を提供しています。加入資格や利用可能な年齢層についての情報が含まれています。
厚生労働省のiDeCo概要情報は、iDeCoの概要に関する情報を提供しています。公的年金との違いや加入の任意性について説明があります。
りそな銀行のiDeCo選び方情報では、iDeCoを選ぶ際の指南が提供されています。掛金拠出額の計算方法についての情報も含まれています。
これらの情報源を参考にして、iDeCoの最新情報を入手し、適切な資料を取得できます。注意して、正確な情報を確認することが大切です。
上記のように出力してくれる時もあれば、資料の説明の後に[1][2]と数字が出力される時もあります。この数字をクリックすると該当の資料が開ける仕組みです。
webライターは必要資料を集めるのにけっこうな手間がかかるので、数秒で提示してくれるのはとてもありがたいですね!
AIと共存できるwebライターは生き残れる!
AIの登場で将来に不安を持つwebライターは多いですが、元々AIは「人間の手間を最大限効率化してサポートする」目的で開発されたものなので、ビビらずに共存する姿勢で臨めば長く活躍できるwebライターになれます。
また、webライターの仕事はディレクター・マーケター・ブロガーの仕事にも大いに活かせるものなので、向上心を持ってスキルや知識を磨けばAIに仕事を取られる心配はないでしょう。
とはいえ私自身もそうですが、webライターになった後に
- 収入が頭打ちになってるな…
- スキルアップしたいけど経験がない…
- どうやって現状を抜け出せばいいんだろう…
という、いわゆる「スランプ」状態に陥った時がありました。
そんな時に力になってくれたのが「かくらぼ」の講師の皆様です。具体的な行動の起こし方をご指導いただいたり、相談に乗ってくださったおかげで月収40万円にたどり着けました。
もしwebライターになってから、なかなか現状打破ができずに悩まれている方は、以下リンクから無料相談に申し込んでみてはいかがでしょうか?

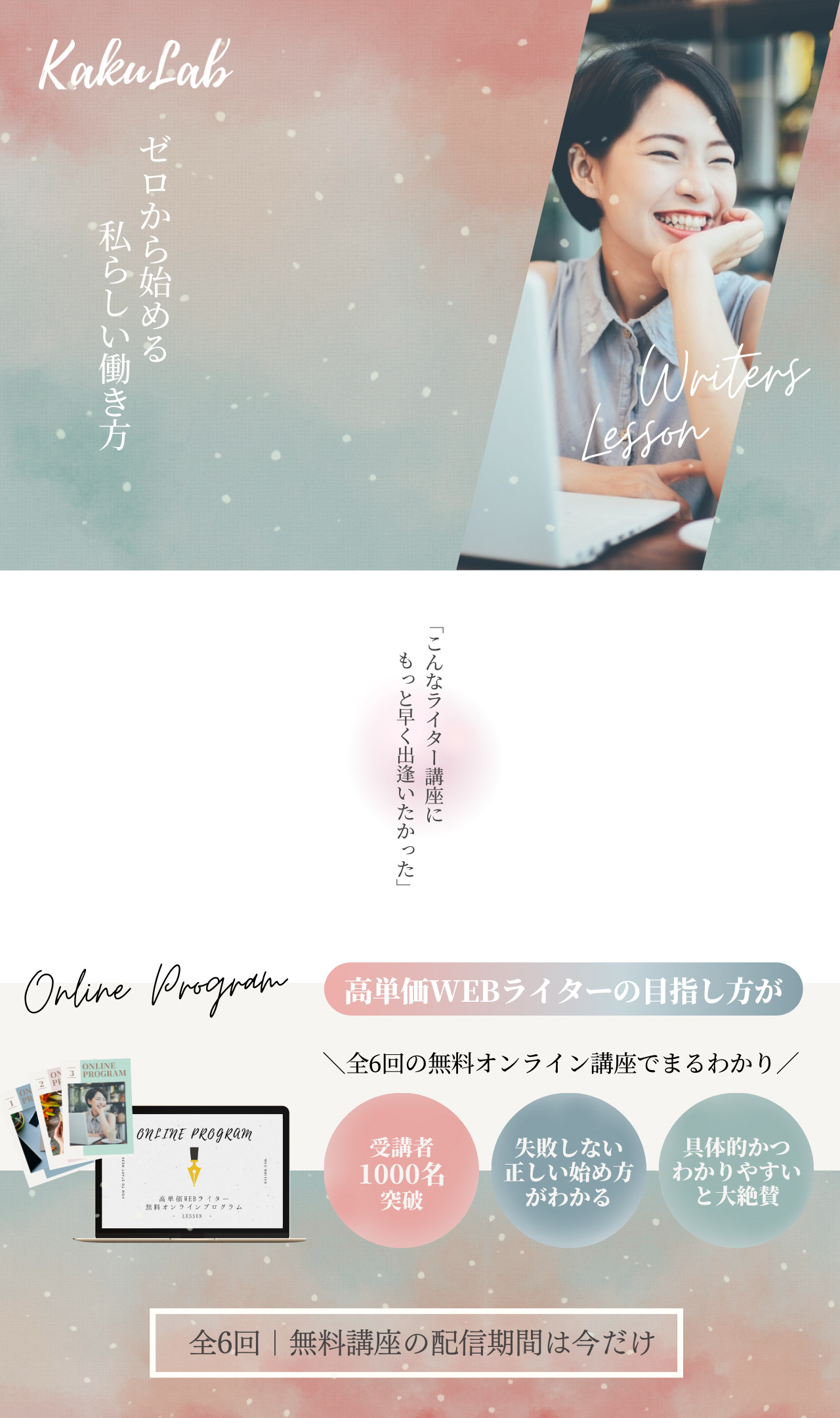
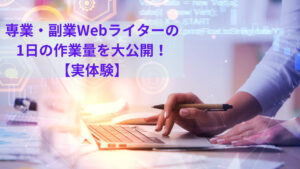


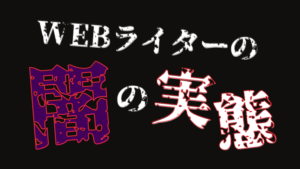
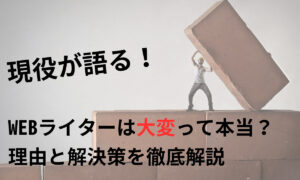
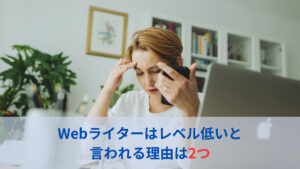

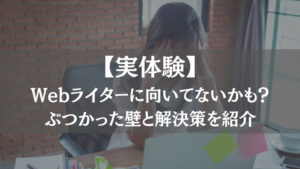

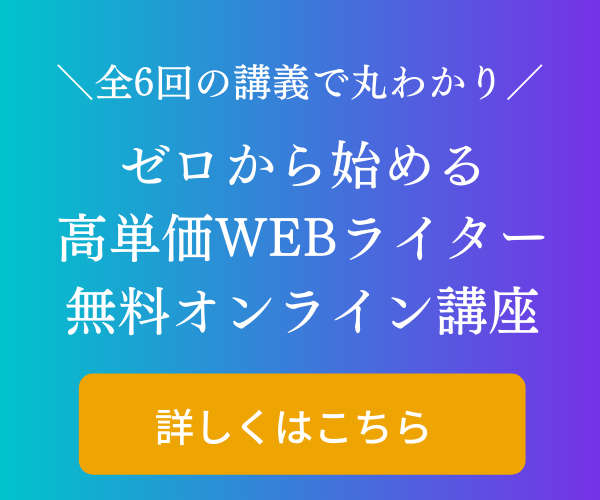
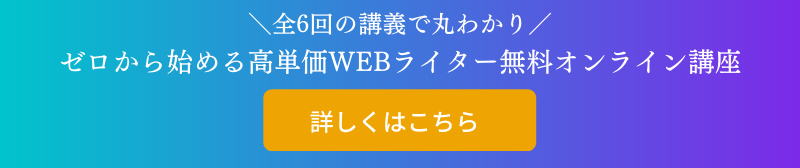
コメント